 お悩み
お悩み自宅で仕事しているんだけど、家賃や電気代って経費にできるのかな?



自宅の家賃や電気代をすべて経費にしても良いのかな?
本記事では、上記のようにお悩みの人に向け、家事按分とは何か、家事按分を適切に計上しないとバレるのかを解説します。
家事按分とは、事業と私生活両方で使用している費用を事業用と私用に振り分けることです。
例えば、自宅で仕事をしている個人事業主は、家賃や電気代、インターネット費用などを家事按分して経費として計上できる可能性があります。
ただし、家事按分を計算する際には、税務署も理解するだけの根拠や証拠を用意しなければなりません。
家事按分の計算や割合が適切でないと、追徴課税が課せられる恐れもあるのでご注意ください。
本記事では、家事按分とは何か、基準や計算が適切でないと税務署にバレるのかを解説します。
家事按分とは?
家事按分とは、事業と私生活の両方で使用している費用を、合理的な基準に基づいて事業用と私用に分けることです。
例えば、自宅でイラスト制作・販売をしている場合、家賃や光熱費、インターネット料金などは仕事とプライベートの両方で使われています。



この場合、事業用に使用した割合を経費として計上可能です
ただし、家事按分を行う際には、客観的に説明できる基準を設定しなければなりません。
適切な割合で按分していない場合や、明確な根拠がない場合、税務署から指摘を受ける可能性があるのでご注意ください。
家事按分の仕訳例
家事按分を正しく処理するためには、事業用の割合を決め、適切に仕訳をしなければなりません。
家事按分の仕訳例を確認してみましょう。
仕訳例:家賃10万円を事業用口座から支払った。自宅で仕事をしており、仕事場の床面積の割合は全体の2割である。家賃を家事按分で経費として計上した。
| 借方 | 借方金額 | 貸方 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 地代家賃 | 20,000円 | 普通預金 | 100,000円 |
| 事業主貸 | 80,000円 |
事業主貸とは、事業用の資金でプライベート用の支出を払ったときに使う勘定科目です。
反対に、事業主借という勘定科目は、プライベート用の資金で事業の支出を払ったときに使う勘定科目です。
- 事業主貸:事業主に貸した
- 事業主借:事業主に借りた
事業主貸と事業主借は混同しがちですが、上記のように覚えておくと間違えにくくなります。
家事按分が不適切だと税務署にバレる?
家事按分は適切に計上する分には問題ありませんが、不適切な按分をすると税務署に指摘される可能性があります。
- 事業用割合が高すぎると税務署に不審に思われやすくなる
- 過去の割合と異なると税務調査の対象になりやすくなる
- 税務調査時に家事按分の証拠・根拠を示さなければならない
それぞれ詳しく解説していきます。
事業用割合が高すぎると税務署に不審に思われやすくなる
家事按分の割合が極端に高い場合、税務署が不適切に経費を計上しているのではないかと疑問を持ちやすくなります。
例えば、自宅の80%以上を事業で使っていると申告すると「本当にここまで事業専用なのか?」と疑われる可能性が高まるでしょう。
特に、イラストレーターの場合、一般的な作業環境では自宅の一部を仕事場として利用するケースがほとんどです。



【談スペースや接客スペースは不要なので、作業環境もそれほど広くはならないはずです
そのため、一般的な水準と比べて高すぎる家事按分の割合を設定すると、税務署のチェックが厳しくなる恐れがあります。
過去の割合と異なると税務調査の対象になりやすくなる
前年まで家賃の30%を事業用として申告していたのに、今年から50%に増やした場合、その理由を明確に説明できなければ、税務署から指摘を受ける可能性があります。
税務署は過去の申告データも併せてチェックしているため、急に按分割合が変わった場合bに「何か不正をしているのでは?」と疑われやすくなります。



事業用スペースを拡張したなどの正当な理由がある場合は、その証拠(間取り図や写真など)を用意しておきましょう
税務調査時に家事按分の証拠・根拠を示さなければならない
税務調査が入った場合、家事按分の根拠を示すよう求められることがあります。
その際、家事按分の割合に関する具体的な証拠がないと、「適当な割合を申告している」と判断され、修正申告を求められる恐れもあるのでご注意ください。
- 作業スペースの写真や間取り図(どの程度事業用として使っているか示すため)
- 電気代の使用状況(仕事用とプライベート用の消費電力量の比較)
- インターネット使用状況(業務用と私用の割合を説明できるデータ)
- 作業時間・スケジュール
また、按分の計算根拠を明確にしておくことも重要です。
「自宅の床面積全体の20%を仕事で使っているから家賃の20%を計上する」などといった根拠を持っておくと、税務署に説明しやすいでしょう。
家事按分が不適切だとバレた場合のペナルティ
不適切な家事按分をしてしまい税務署から指摘を受けると、過少申告加算税などといったペナルティが発生する恐れがあります。
- ペナルティ
- 過少申告加算税
- 延滞税
- 重加算税
それぞれ詳しく解説していきます。
過少申告加算税が課せられる
過少申告加算税は、申告した税額が本来納めるべき税額より少なかった場合に課される税金です。
【過少申告加算税の税率】
| 修正申告書の提出が税務調査の通知前だった | 過少申告加算税は課されない |
|---|---|
| 期限内に申告書を提出しており、修正申告書を提出・更生した場合 | 追加で納税する税額の10% 期限内申告税額と50万円のうち、多い方を超える部分は15% |
| 修正申告書の提出は税務調査の通知を受けた後だが、調査による更生を予知していたわけではない場合 | 追加で納付する税額の5%期限内 申告税額と50万円のうち、多い方を超える部分は10% |
例えば、家事按分を過大に計上し、本来の所得税額よりも10万円少なく申告していた場合を考えてみましょう。
この場合では、追加で納める10万円のうち、1万円(10%)が過少申告加算税として加算されます。
延滞税が課せられる
延滞税は、本来の納税期限までに支払うべき税金を納めなかった場合に発生する税金です。
家事按分の誤りによって税金を追加で納めることになった場合、納付が遅れた期間に応じて延滞税が加算されます。
【延滞税の税率】
| 納期限の翌日から2ヶ月以内 | 下記のいずれか低い方 ・年7.3% ・特例基準割合+1%(令和7年の場合は2.4%) |
|---|---|
| 納期限の翌日から2ヶ月超 | 下記のいずれか低い方 ・年14.6% ・特例基準割合+7.3%の低い方(令和7年の場合は8.7%) |
重加算税が課せられる
重加算税は、故意に税金をごまかしたと判断された場合に課されるペナルティです。
過少申告加算税よりも税率が高く、税務署が「隠蔽または仮装があった」と判断した場合に適用されます。
【重加算税の税率】
| 申告書を提出していた場合 | 原則として35% |
|---|---|
| 申告書を提出していなかった場合 | 原則として40% |
例えば、家事按分を明らかに不自然な割合で計上し、税務調査時に根拠のない虚偽の説明をした場合や、帳簿を改ざんしていた場合は重加算税が課される恐れがあります。
家事按分の根拠の例
家事按分を適正に行うためには、合理的な根拠をもとに事業用と私用の割合を決める必要があります。
根拠が不明確な場合、税務署から指摘を受けるリスクが高まるからです。
家事按分の根拠となるものは、主に下記の通りです。
- 面積割合
- 時間割合
- 日数割合
それぞれ詳しく解説していきます。
面積割合
面積割合とは、自宅のうち事業用に使用しているスペースの割合を基準に按分する方法です。
例えば、イラストレーターが自宅の一室を作業部屋として使用している場合、その部屋の面積が自宅全体のどのくらいの割合を占めているかで、家賃や光熱費などの経費を按分できます。
面積割合を活用する場合は「(事業用スペースの面積÷自宅全体の面積)×100」で計算できます。
具体例を見ていきましょう。
- 自宅面積:50㎡
- 仕事部屋の面積:10㎡
上記の場合は「10㎡÷50㎡=20%」で家事按分を計算できます。



上記の例であれば、家賃の20%を経費として計上できる可能性があります
時間割合
時間割合とは、家事按分の対象となる費用を、仕事に使っている時間の割合で按分する方法です。
時間割合は、電気代や通信費などの変動費の家事按分で適用されることが多いです。
時間割合を活用する場合は「(事業に使用した時間÷1日の総使用時間)×100」で計算できます。



例えば、自宅で仕事をしており、インターネットの回線を1日8時間使用している場合を考えてみましょう
この場合は「8時間÷24時間=33.3%」となり、電気代やインターネット料金の約33%を経費として計上できます。
ただし、税務調査が行われた場合は「本当にその時間だけ仕事をしていたのか」と疑われる可能性もあります。



そのため、作業ログやスケジュール帳を残しておくと良いでしょう
日数割合
日数割合とは、1ヶ月または1年のうち、何日間を事業用に使用していたかを基準に按分する方法です。



仕事をする日が決まっている場合に適用しやすい方法といえるでしょう
日数割合を活用する場合は「(事業に使用した日数÷1ヶ月または1年の総日数)×100」で計算できます。
具体例とともに見ていきましょう。
- 1ヶ月30日のうち、20日間は仕事をしていた
- 10日間はプライベートでしか使っていない
上記のケースでは家事按分を「20日÷30日=66.6%」と計算できます。
日数割合は、仕事をする日が明確な場合に有効ですが、日ごとに仕事とプライベートの境界が曖昧な場合には適用しづらいこともあるでしょう。



また、税務調査に備えて、カレンダーや作業記録をつけておくことも大切です
家事按分を適切に計上するコツ
家事按分を適切に行えば、税負担を抑えられる可能性があります。
ただし、不適切な家事按分を設定してしまうと、税務調査のリスクが上がるので注意しなければなりません。
家事按分を適切に計上するコツは、主に下記の通りです。
- 家事按分の根拠を用意しておく
- 一度決めた家事按分を継続する
- 税理士に相談してみる
それぞれ詳しく解説していきます。
家事按分の根拠を用意しておく
家事按分を行う際、合理的な根拠を明確にしなければなりません。
税務署は「どのような基準で按分したのか」を重視するため、事業用と私用の割合を示す客観的なデータを準備しましょう。
根拠の具体例となるものは、主に下記の通りです。
| 家事按分の決定方法 | 根拠の例 |
|---|---|
| 面積割合 | 事業専用の部屋が何㎡あるかを計測し、自宅全体の面積と比較する |
| 時間割合 | 毎日の作業時間を記録し、生活時間全体と比較する |
| 日数割合 | カレンダーや作業記録をつけ、1ヶ月・1年間の事業日数を把握する |
税務調査では「適当に決めました」といった説明では通用しません。



計算方法を明確にし、書面やデータで証拠を残しておきましょう
一度決めた家事按分を継続する
家事按分の割合を毎年大きく変更すると、税務署に不審に思われやすくなります。
例えば、前年は家賃の20%を経費にしていたのに、今年から50%に増やすと、税務署から「なぜ大幅に変わったのか?」と疑われる可能性があります。
引っ越して仕事部屋の面積が増えたなど、変更が必要な場合は、下記の対策をしておきましょう。
- 変更理由を明確にする(引っ越しや事業内容の変化など)
- 過去の記録を保持し、新しい按分割合と比較できるようにする
- 税理士に相談して、税務署に納得してもらえる根拠を作る
税理士に相談してみる
家事按分は個人の判断で行うことができますが、適用方法に迷う場合は税理士に相談するのがおすすめです。
特に、下記のように考えている場合は、税理士への相談も検討しましょう。
- 按分割合の決定に自信がない
- 税務調査を受けるリスクを減らしたい
- 過去に適用した割合を見直したい
税理士に相談すれば、過去の判例や税務調査の傾向を踏まえた適切なアドバイスが得られるため、リスクを最小限に抑えられます。
家事按分を計上するときの注意点
家事按分は適切に行えば節税につながりますが、不適切な計上をすると税務署に否認される可能性があります。
また、賃貸住宅の場合、そもそも事業利用が禁止されていることもあるのでご注意ください。
本章では、家事按分を計上するときの注意点を解説していきます。
事業利用が禁止されている賃貸住宅もある
賃貸住宅では、契約によって事業利用が制限されている場合があります。
自宅で仕事をしている人が、家賃の一部を経費として家事按分する場合、そもそも自宅を事業用として使用できるのかを確認しておきましょう。
事業利用が禁止されている賃貸住宅の例は、主に下記の通りです。
| 契約内容 | 概要 |
|---|---|
| 住居専用契約 | 住居としてのみ使用可能で、事業利用が禁止されている |
| 事業利用の届け出が必要 | 管理会社やオーナーの許可がないと、事業用利用が認められない |
| 商業活動禁止の規定 | 法人登記や業務用の来客対応などが禁止されている場合がある |
住居専用契約の場合、事業利用が発覚すると契約違反となり、退去するよう言われる恐れもあるのでご注意ください。
コワーキングスペース・カフェでの仕事と家事按分の割合で揉める場合がある
コワーキングスペースやカフェなどといった自宅以外にて仕事をしている場合、家事按分の割合をどのように決めるかが問題になることがあります。
例えば、普段はカフェやコワーキングスペースで作業しているのに、家賃の50%を家事按分するのは認められない可能性があります。
税務署が調査を行った際、「自宅ではどれくらい仕事をしているのか?」と聞かれたときに、合理的な説明ができなければ按分割合を否認される可能性があるのでご注意ください。
合理的な説明をするためにも、下記の方法などで対策しておくと良いでしょう。
- 仕事場所の割合を記録する
- 家事按分の割合を適切に調整する
- 税務調査時の説明を準備する
例えば、週5日のうち3日はカフェで仕事をし、2日は自宅で作業している場合、自宅の家賃を50%按分するのは不適切とみなされる恐れがあります。
この場合、①自宅の事業用割合を低めに設定するか、②カフェ・コワーキングスペースの利用費用を経費として計上することを検討しましょう。
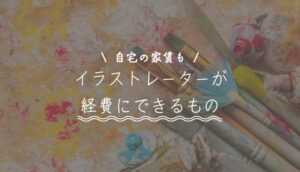
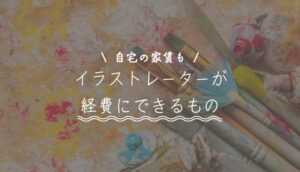
クラウド会計を使えば家事按分を計算・記録しやすい



家賃は面積割合、電気代は時間割合で家事按分を計算しているけど、とにかく大変



経費の計算や確定申告を楽にする方法は、ないかな?
上記のようにお悩みの人は、クラウド会計を使うことも検討しましょう。
クラウド会計では、家事按分の割合や按分する勘定科目を設定可能です。



家事按分の設定を完了させれば、年末にまとめて家事按分を計算してくれます
クラウド会計は複数のものがありますが、イラストレーターにおすすめのものは下記の通りです。
| クラウド会計 | 特徴 |
|---|---|
| やよいの青色申告オンライン | 最大1年間の無料体験が可能! クラウド会計の料金を抑えたい方に最適 |
| マネーフォワードクラウド確定申告 | クラウドワークスなどイラストレーターが利用するサービスとの連携機能が豊富 |
| freee | 簿記・会計の知識がなくても操作しやすいシンプルな機能が魅力 |
クラウド会計の利用には年間10,000円程度の費用がかかりますが、毎月1,000円弱で家事按分を漏れなく計算できると考えればお得に感じるのではないでしょうか。
イラストレーターにおすすめのクラウド会計は「イラストレーターにおすすめのクラウド会計3選|メリットや選び方とは?」でも、詳しく紹介しています。


家事按分についてよくある質問
最後に、家事按分についてよくある質問を回答とともに紹介していきます。
- 家事按分ができないケースはどんなものがありますか?
-
家事按分は、事業で使った分だけを経費にできるというルールに基づいています。
そのため、以下のようなケースでは家事按分が認められません。
- 完全にプライベートの支出であるもの
- 仕事とプライベートの境界が明確でないもの
- 契約上、事業利用が禁止されているもの
- 家事按分が認められるものにはどんなものがありますか?
-
家事按分が認められるかどうかは、事業として利用していることが明確かどうかです。
下記のようなものは、事業利用部分に限り家事按分が認められる可能性があります。
- 自宅の家賃(賃貸の場合)
- 電気代
- インターネットの利用料金
- スマホの利用料金
- 個人事業主は税務調査でどこまで調べられますか?
-
税務調査では、経費の適正性を確認するために詳細な調査が行われます。
主な調査内容は、下記の通りです。
- 経費の領収書・請求書の確認
- 銀行口座やクレジットカードの明細
- 仕事場の確認
- 電気代は家事按分できますか?
-
自宅で仕事をしている場合、電気代を家事按分できる可能性があります。
ただし、経費として計上できる分は、事業利用部分のみです。
- 車は家事按分できますか?
-
事業で使用する部分に限り、車の維持費やガソリン代を按分できます。
ただし、車を家事按分する場合、家事按分を適切に設定しなければなりません。
- トイレは家事按分できますか?
-
基本的に、トイレの家事按分は認められません。
トイレは、仕事とプライベートの区別が難しいため、経費として計上するのは難しいからです。
- 家事按分の割合の決め方にはどんなものがありますか?
-
家事按分の割合は、合理的な基準に基づいて決定する必要があります。
代表的な方法は、下記の通りです。
- 面積割合
- 時間割合
- 日数割合
【まとめ】
自宅で仕事をすることが多いイラストレーターにとって、家事按分を適切に設定することは非常に重要です。
家事按分を設定すれば、家賃や電気代、インターネット料金などの一部を経費として計上できるからです。
ただし、家事按分として設定できるのは「事業に支出した割合」のみであり、税務署も納得する根拠を用意しなければなりません。
例えば、自宅の家賃を家事按分したいのであれば、床面積で按分の割合を決定しても良いでしょう。
家事按分の割合について悩んだときや、割合を変更したい場合には、税理士に一度相談してみることもおすすめします。




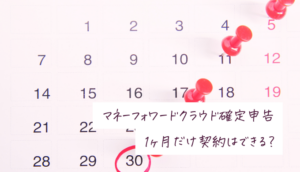
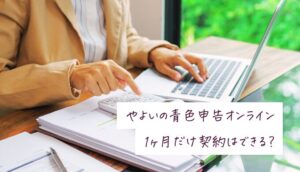

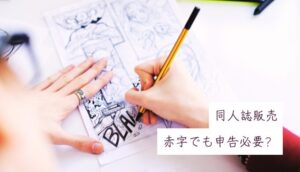
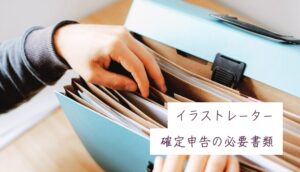
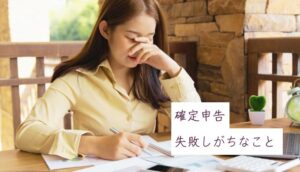

コメント