 お悩み
お悩み減価償却って何だろう?



先日、パソコンを買ったんだけど、そのまま経費として計上して良いですか?
本記事では、上記のようにお悩みのイラストレーターに向け、減価償却について解説していきます。
減価償却(げんかしょうきゃく)とは、高額なパソコンなどを購入したときに、費用を一度に経費として処理せず、数年に分けて経費として計上する方法です。



イラストレーターの場合は、パソコンや液タブを買ったときに減価償却が必要な場合があります
パソコンを購入した際に、1回で経費として計上すると確定申告時に指摘を受ける恐れがあるのでご注意ください。
本記事では、イラストレーター向けに減価償却とは何か、どのように処理すれば良いのかを解説します。
イラストレーターの経費については、下記の記事で詳しく解説しているので、よろしければ併せてお読みください。
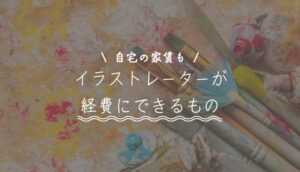
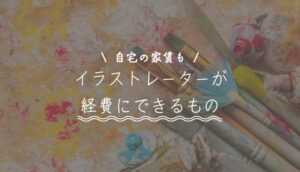
減価償却とは
減価償却(げんかしょうきゃく)とは、パソコンなど高額な設備を購入した際に、費用を一度に経費として計上せず、複数年に分けて少しずつ経費として計上していく会計処理です。
例えば、1台30万円のパソコンを購入した場合を考えてみましょう。
30万円をその年の経費として一括で計上するのではなく「数年間使うものだから、費用も複数年に分けて計上しましょう」というのが減価償却です。
減価償却は税務上のルールであり、特定の条件に当てはまる資産を購入した場合は、原則として減価償却による経費処理が義務付けられています。



原則として、10万円超えの資産を購入した場合は、減価償却をしなければなりません
次章では、個人で働くイラストレーター向けに、減価償却のルールについて確認していきましょう。
個人で働くイラストレーターの減価償却ルール
10万円超えの資産を購入した場合は、減価償却しなければなりません。
個人で働くイラストレーターが理解しておくべき減価償却のルールは、主に下記の通りです。
- 10万円超えの資産は減価償却が義務付けられている
- 計算方法は「定額法」を用いる
それぞれ詳しく解説していきます。
10万円超えの資産は減価償却が義務付けられている
個人事業主であるイラストレーターが業務用に使う備品を購入した場合、その金額によって処理方法が異なります。
購入金額が10万円を超える資産は、減価償却が義務付けられているからです。



10万円以下で購入したものは「消耗品費」として一括でその年の経費にできます
ただし、青色申告を選択している個人事業主の場合は購入金額が30万円未満のものであれば「少額減価償却資産の特例」を利用して一括償却することも可能です。



個人事業主が適用できる減価償却の特例は、本記事の後半で紹介します
計算方法は「定額法」を用いる
個人事業主が減価償却を行う際には「定額法」という計算方法を使います。
定額法とは、毎年同じ金額を経費として計上していく方法です。
例えば、購入金額40万円のパソコンを購入した場合を考えてみましょう。
- 購入金額:40万円
- 法定耐用年数:4年
上記のケースでは「40万円÷4年=10万円」を毎年の経費として計上していきます。



なお、年の途中でパソコンを購入した場合には、初年度の減価償却費は月割で計算します
具体例ではサラッと紹介してしまいましたが、減価償却の対象となる資産は「法定耐用年数」が決まっています。



イラストレーターが購入する資産の法定耐用年数の一覧は、本記事の後半で紹介します!
個人で働くイラストレーターが使える減価償却の特例
減価償却は基本的に数年間にわたって資産を分割して経費化する制度ですが、一定の条件を満たせば、特例を適用し、より簡単に処理できます。
個人で活動しているイラストレーターの場合は、減価償却の手間を減らすためにも、特例の適用を検討していきましょう。
詳しく紹介していきます。
一括償却資産
取得価額が10万円超〜20万円未満の資産については「一括償却資産」として処理できます。
法定耐用年数に関係なく3年間で均等に償却できる制度



個人事業主であれば、白色申告でも青色申告でも利用できます
例えば、15万円の液晶タブレットを購入した場合には、5万円ずつを3年間にわけて経費計上できます。
- 耐用年数を調べる必要がなくなる
- 初年度の月割計算が不要となる



上記のように、減価償却の処理のしやすさがメリットといえるでしょう
ただし、一括償却資産として処理した資産は、原則として帳簿上に3年間は載せ続ける必要があります。
少額減価償却資産の特例(青色申告のみ)
もうひとつの重要な特例が「少額減価償却資産の特例」であり、取得価額が30万円未満の資産であれば、その年に全額一括で経費計上できる制度です。



例えば、25万円の液タブやパソコンなどを購入した場合も、一括で経費として計上できます
減価償却の手間もなくせますし、経費のコントロールをしやすくなるのもメリットといえるでしょう。
少額減価償却資産の特例は、青色申告を選択している個人事業主のみが利用できる制度です。
また、少額減価償却資産の特例は、1年間で合計300万円までしか特例を適用できない点にも注意しましょう。
【仕訳例付】資産購入から減価償却までの流れ
イラストレーターが業務用にパソコンや液タブなどの高額機材を購入した場合、経費として一括で処理するのではなく、減価償却をしなければなりません・
資産を購入してから減価償却するまでの流れを仕訳例とともに見ていきましょう。
10万円未満の資産を購入した場合
購入金額が10万円未満であれば、減価償却の必要はなく、その年に「消耗品費」として一括で経費計上できます。
90,000円の液晶モニターを購入し、銀行振込で支払った
| 借方 | 借方金額 | 貸方 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 90,000円 | 普通預金 | 90,000円 |
上記のように、10万円未満の資産を購入した場合には、減価償却は必要なく、一括で経費として処理できます。
10万円以上20万円未満の資産を購入した場合
10万円以上20万円未満の資産を購入した場合は「一括償却資産」か「少額減価償却資産の特例」を適用して処理できます。
本記事では、一括償却資産を適用した場合の仕訳例を紹介します。
18万円の液タブを現金で購入した
| 借方 | 借方金額 | 貸方 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 器具備品 | 180,000円 | 現金 | 180,000円 |
上記のように、10万円以上の資産を購入した場合、一括で経費計上できないので器具備品勘定などで資産として処理します。
そして、期末(個人事業主の場合12月31日)に、減価償却費の計上をします。
12月31日に液タブの減価償却費を計上した
| 借方 | 借方金額 | 貸方 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 60,000円 | 減価償却累計額 | 60,000円 |
一括償却資産を適用した場合は購入した資産にかかわらず、3年間で減価償却費を計上します。
そのため、1年分の減価償却費は「18万円÷3年間=60,000円」と計算可能です。
20万円以上30万円未満の資産を購入した場合
20万円以上30万円未満の資産を購入した場合、一括償却資産は適用できず、少額減価償却資産の特例のみ適用できます。



ただし、少額減価償却資産の特例は青色申告を選択している場合しか、利用できません
28万円のパソコンをクレジットカードで購入した
| 借方 | 借方金額 | 貸方 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 器具備品 | 280,000円 | 未払金 | 280,000円 |
少額減価償却資産の特例を適用する場合、一気に減価償却費を計上できます。
12月31日に少額減価償却資産の特例を適用して、減価償却費を一括で計上した
| 借方 | 借方金額 | 貸方 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 280,000円 | 減価償却累計額 | 280,000円 |
30万円以上の資産を購入した場合
30万円以上の資産を購入した場合は、特例を適用できないため、法定耐用年数にしたがって減価償却をしなければなりません。
1月1日に35万円の液タブを購入し、銀行振込で支払った
| 借方 | 借方金額 | 貸方 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 器具備品 | 350,000円 | 普通預金 | 350,000円 |
液タブの法定耐用年数は4年とされているので、1年分の減価償却費は「35万円÷4年=87,500円」です。
12月31日に液タブの減価償却費を計上した
| 借方 | 借方金額 | 貸方 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 87,500円 | 減価償却累計額 | 87,500円 |
イラストレーターが購入する主な資産の耐用年数
減価償却を行う際には「法定耐用年数」に基づいて毎年の償却費を計算する必要があります。
法定耐用年数は国税庁が定めており、資産の種類によって異なります。
イラストレーターが業務で使用する主な資産の耐用年数は、下記の通りです。
- パソコン・ノートPC:4年
- 液タブ・ペンタブ:4年
- プリンター・スキャナーなどの周辺機器:5年
- デスク・椅子・書棚などの事務用什器:15年



ただし、購入した資産ただし、購入した資産が30万円未満の場合は、法定耐用年数に関係なく特例を適用できます
個人で働くイラストレーターが減価償却をする際の注意点
個人で働くイラストレーターは、減価償却時や資産購入時に下記などに注意する必要があります。
- 事業・プライベート兼用の資産は家事按分しなければならない
- 免税事業者は税込価格で処理をしなければならない
- 分割払いでの購入も減価償却の特例を適用できる
- 資産そのものだけでなく関連費も経費として計上できる
それぞれ詳しく解説していきます。
事業・プライベート兼用の資産は家事按分しなければならない
パソコンやプリンター、液タブなど仕事だけでなく、プライベートでも使用する資産を購入した場合、全額を経費として計上することはできません。
仕事とプライベート兼用で使用するものを購入した場合は、業務に使用した割合のみ経費で計上する「家事按分」と呼ばれる処理をする必要があります。
20万円のパソコンを仕事6割、プライベート4割で使用している
この場合は「20万円×60%=12万円」のみを経費として計上可能です。
ただし、家事按分は自由に設定できるわけではなく、使用する時間や仕事部屋の床面積など根拠となる証拠を用意しておく必要があります。



根拠なく、自分にとって都合の良い家事按分を設定してしまうと、税務署に指摘される恐れがあるのでご注意ください
家事按分については「家事按分を適切に設定しないと税務署にバレる?計算方法と注意点」の記事でも、詳しく紹介しているので、よろしければ併せてお読みください。


免税事業者は税込価格で処理をしなければならない
消費税の免税事業者は、原則として税込価格で経費処理を行います。
例えば、税込33万円の液タブを購入した場合、消費税を差し引いて処理する必要はなく、全額を取得価額として減価償却可能です。



課税事業者と免税事業者は、処理方法が異なるため、自身の立場を確認しておきましょう
分割払いでの購入も減価償却の特例を適用できる
分割払いで高額資産を購入した場合も、購入時点で全額の所有権が移転する契約であれば、減価償却の特例を適用できます。
例えば、クレジットカードで一括35万円のパソコンを買った場合、支払いは翌月以降でも、購入時に資産として計上しなければなりません。
資産そのものだけでなく関連費も経費として計上できる
資産を計上する際には、パソコンや液タブなどの本体費用のみだけでなく、下記のような関連費も経費として計上しなければなりません。
- 設置費用
- 配送料
- 初期設定費用
- 保証サポート費用
クラウド会計なら減価償却の処理も簡単に行える
ここまで個人で働くイラストレーター向けに、減価償却の処理方法について解説してきました。
しかし、イラスト制作や販売で忙しい方にとっては「自分で処理できるのか」「購入金額ごとに間違えず処理するのが難しい」と感じているのではないでしょうか。
個人で働くイラストレーターにおすすめのクラウド会計は、下記の通りです。
| クラウド会計 | 特徴 |
|---|---|
| やよいの青色申告オンライン | 最大1年間の無料体験が可能! クラウド会計の料金を抑えたい方に最適 |
| マネーフォワードクラウド確定申告 | クラウドワークスなどイラストレーターが利用するサービスとの連携機能が豊富 |
| freee | 簿記・会計の知識がなくても操作しやすいシンプルな機能が魅力 |
クラウド会計を利用すれば、減価償却の計算や仕訳などを自動化できます。



どれも無料体験可能ですので、複数試してみて、自分に合うものを選ぶと良いでしょう!
イラストレーターにおすすめのクラウド会計は「イラストレーターにおすすめのクラウド会計3選|メリットや選び方とは?」でも、詳しく紹介しています。


イラストレーターの減価償却についてよくある質問
最後に、イラストレーターの減価償却についてよくある質問を回答とともに紹介していきます。
- イラストレーターの経費として認められる費用は何ですか?
-
イラストレーターの経費として認められる費用は、主に下記の通りです。
- イラスト制作に使用した画材代
- パソコン代・周辺機器代
- イラスト制作のソフト代
- クラウド会計の使用量
- インターネット費用
- スマホの使用料金
- イラスト制作・販売の資料・書籍代
- 自宅の家賃・作業場の家賃
- 自宅の電気代・作業場の電気代
- カフェ・コワーキングスペースの作業代
- セミナー受講費用
- 固定資産税や自動車税
- 損害保険料
ただし、上記の費用をすべて経費にできるわけではなく、仕事に関わる費用のみを経費として計上できます。
- イラストレーターが画材を買ったら勘定科目は何を使えば良いですか?
-
イラストレーターが画材を買った場合、勘定科目は「消耗品費」を使用することが一般的です。
ただし、購入した画材が高額(10万円超)の場合には、資産として計上し、減価償却をしなければなりません。
- イラストレーターが購入した液タブは経費になりますか?
-
イラストレーターが仕事に使用する目的で購入した液タブは、経費として計上できます。
ただし、液タブを趣味などプライベートでも使用する場合、家事按分して計上しなければなりません。
- イラストレーターが報酬を源泉徴収されない場合はどうすれば良いですか?
-
源泉徴収の義務は仕事を依頼した側の企業側に課せられています。
そのため、源泉徴収されなくても、イラストレーター側に問題が発生することはありません。
- カメラを減価償却する場合の耐用年数は何年ですか?
-
参考資料の撮影など仕事目的で購入したカメラの法定耐用年数は5年です。
例えば、35万円のカメラを購入した場合「35万円÷5年=7万円」と減価償却費を計算します。
【まとめ】10万円以上のものを買ったら減価償却をしましょう
パソコンや液タブなどといった10万円以上の品物を購入したら、全額経費として処理するのではなく、減価償却をしなければなりません。
開業届を提出し、青色申告を適用している場合には、減価償却の特例を使える場合もあります。
また、減価償却の計算や仕訳の手間を減らしたい場合には、クラウド会計を利用すれば会計処理や確定申告の手間を減らせるのでおすすめです。
クラウド会計には複数ありますが、個人で働くイラストレーターや副業イラストレーターの場合は、下記を利用するのが良いでしょう。
| クラウド会計 | 特徴 |
|---|---|
| やよいの青色申告オンライン | 最大1年間の無料体験が可能! クラウド会計の料金を抑えたい方に最適 |
| マネーフォワードクラウド確定申告 | クラウドワークスなどイラストレーターが利用するサービスとの連携機能が豊富 |
| freee | 簿記・会計の知識がなくても操作しやすいシンプルな機能が魅力 |
クラウド会計を利用すれば、減価償却時の処理だけでなく、日々の経費処理や確定申告書の作成の手間を軽減可能です。



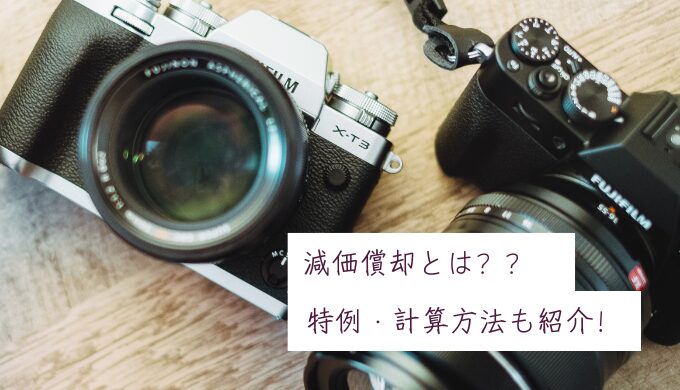
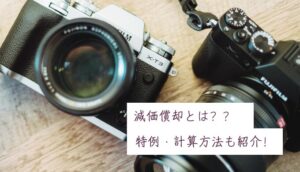

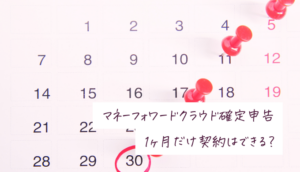
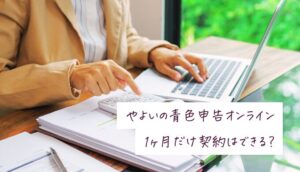

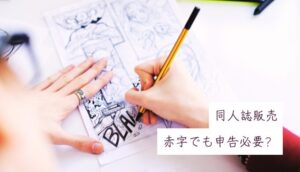
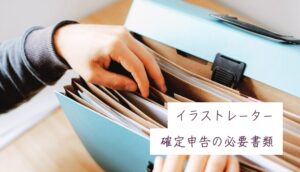
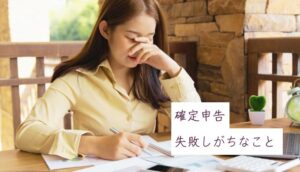

コメント