 お悩み
お悩みフリーランスのイラストレーターとして活動しているんだけど、税金や社会保険料が高くて辛い……



毎年、確定申告の時期になって「もっと節税対策できたのかな」と悩むのをやめにしたい
本記事では、上記のようにお悩みの方に向け、個人で働くイラストレーターの節税対策の年間スケジュールを紹介します。
- 確定申告・節税対策の年間スケジュール
- 年間を通して節税対策を行うコツ
- 個人事業主・フリーランスの税金の支払いスケジュール
個人事業主やフリーランスのイラストレーターとして活動する中で、避けて通れないのが「確定申告」と「節税対策」です。
確定申告は2月16日から3月15日の間に行う必要がありますが、節税対策は年間を通して計画的に行うことが重要です。
また、個人で働くイラストレーターは税金や社会保険料を自分で納める必要があるので、支払い時期を把握しておき、資金繰りに困らないようにしましょう。
本記事では、1年を通じてイラストレーターが取り組むべき節税対策と税金のスケジュールを、月ごとにわかりやすく整理しました。
【個人で働くイラストレーター向け】確定申告・節税対策の年間スケジュール
個人事業主として働くイラストレーターの確定申告や節税対策の年間スケジュールは、以下の通りです。
| 月 | やるべきこと |
|---|---|
| 1月 | ・前年の売上・経費を集計する ・領収書・レシートを整理する ・所得控除・税額控除(医療費控除・ふるさと納税)などの証明書を集計・整理する |
| 2月・3月 | ・確定申告をする ・消費税申告(課税事業者のみ)をする ・今年の売上予測を立てる |
| 4月 | ・小規模企業共済やiDeCo、国民年金基金の掛金計画を立てる ・固定資産の購入計画を立てる |
| 5月 | ・住民税や国民健康保険の通知を確認する ・サブスク契約の見直しをする |
| 6月 | ・ふるさと納税をする(1回目) |
| 7月 | ・上半期の売上・経費の集計をする ・今年の売上予測の調整をする ・固定資産・備品の購入(Primeデー) |
| 8月 | ・固定資産・備品・経費の入力漏れがないか確認しておく |
| 9月 | ・ふるさと納税をする(2回目) |
| 10月 | ・年末までの売上見込みを再計算する ・小規模企業共済やiDeCo、国民年金基金の掛金計画の調整をする ・追加で計上する経費はないか確認する |
| 11月 | ・売上が予測を大きく上回れば追加でふるさと納税をする |
| 12月 | ・年内に計上したい経費を支出する ・来年の売上・経費を予測する |
それぞれ詳しく解説していきます。
【1月】前年の売上・経費を集計する
年が明けたら、前年1年間(1月1日~12月31日)の売上と経費を集計しましょう。



売上については、請求書や入金明細、通帳の履歴などから確認します
複数の取引先から報酬を得ている場合は、見落としのないように、案件ごとにリスト化すると便利です。
経費についても同様に、帳簿や会計ソフトに入力した内容を見直して、業務に必要だった支出を漏れなく集計しましょう



これらの集計を年が明けたらすぐに行っておくことで、確定申告シーズンに慌てなくてすみます
【1月】領収書・レシートを整理する
経費として計上するためには、支出の証拠として領収書やレシートの保管が重要となります。
特に、紙で受け取ったものは、時間が経つとインクが薄くなったり、紛失したりすることがあるため、1月のうちにまとめて整理しておくのがおすすめです。



私の場合は、日付順にファイルでまとめてしまっています
なお、領収書がない支出については、出金伝票を作成することで経費に計上可能です。
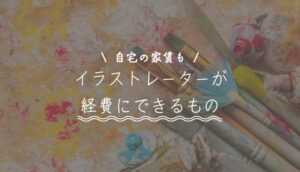
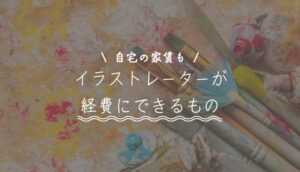
【1月】所得控除・税額控除(医療費控除・ふるさと納税)などの証明書を集計・整理する
確定申告に向けて、売上・経費の確認だけでなく、所得控除に関する証明書の収集も行いましょう。
所得控除や税額控除は、名前の通り、所得や所得税額から直接控除できる支出であり、代表的なものは以下の通りです。
| 所得控除・税額控除の種類 | 必要資料 |
|---|---|
| 社会保険料控除 | 国民健康保険や年金の支払い証明書 |
| 医療費控除 | その年に払った医療費の明細書・領収書 |
| 生命保険料控除 | 生命保険料控除証明書 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCoなど) |
| 寄付金控除 | ふるさと納税などの寄付証明書 |
| 住宅ローン控除 | ・住宅借入金等特別控除額の計算明細書(国税庁HPでダウンロード可能) ・住宅借入金等特別控除証明書 ・登記事項証明書 ・売買契約書または工事請負契約書のコピー ・住民票の写し |



支出のタイミングによっては、控除を適用できることを忘れがちなので、早めに準備しておきましょう
また、所得控除や税額控除を適用する場合には、確定申告時に証明書類を提出もしくは保管しておく必要があります。
e-taxによる申告の場合には、一部の書類提出が免除されますが、それでも証明書類を保管しておかなければなりません。



所得控除・税額控除の書類についても、領収書と同様にファイルでひとまとめにしています
【2月・3月】確定申告をする
2月16日から3月15日までの間は、いよいよ確定申告の提出期間です。
1月に集計・整理した売上・経費・控除証明書をもとに、所得税の申告書を作成し、税務署に提出します。
提出方法は、3通りがありますが、オンラインで完結でき、青色申告特別控除の適用要件にも含まれるe-Taxがおすすめです。
- 電子申告(e-Tax)
- 郵送
- 窓口持参



クラウド会計を利用していれば、データ連携により申告が完了するものも多く、郵送や紙の手書きよりも効率的です
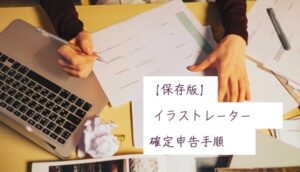
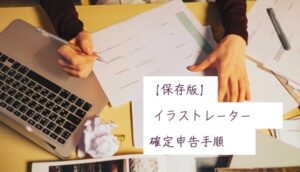


【2月・3月】消費税申告(課税事業者のみ)をする
前々年の売上が1,000万円を超えている場合やインボイスの発行事業者である場合には、消費税の課税事業者となるため、所得税と並行して消費税申告もしなければなりません。



確定申告よりも若干期限は長く、3月末までに申告・納付を完了させる必要があります
消費税申告では、売上に対する消費税(預かり分)から、経費で支払った消費税(支払分)を差し引いた金額を計算します。
帳簿上で消費税額を区分していないと正確な申告が難しくなるため、早めに対応しましょう。



消費税申告についても自分で計算・申告するのは非常に大変なので、税理士に相談するか、クラウド会計を利用することをおすすめします
【2月・3月】今年の売上予測を立てる
確定申告がひと段落したら、今年の見込み売上や利益を予測しておくと、その後の節税計画や資金管理がしやすくなります。



確定申告直後の節税・納税に関するアンテナが高い時期に計画してしまうのがおすすめです!
前年の実績を参考に、受注ペースや単価の傾向を分析しておきましょう。



もし、大型案件や継続的な取引の見込みがある場合は、それも織り込んでおくと精度が高まります
売上予測を立てることで、年内にどの程度の経費を使えるか、控除枠を活かす余地があるかなどが見えてくるはずです。
また、売上が1,000万円に近い場合は、将来的な消費税の課税対象となる可能性があるため、事前に意識しておきましょう。
インボイスに登録していなくて、消費税の課税事業者になりたくないのであれば、売上を1,000万円未満に抑える工夫も必要となってくるはずです。
【4月】小規模企業共済・iDeCo・国民年金基金の掛金計画を立てる
4月は、新年度のスタートとして、節税につながる制度の利用を見直すのに適したタイミングです。
個人事業主の資金形成や節税におすすめの制度は、以下の通りです。
| 制度名 | 概要 |
|---|---|
| 小規模企業共済 | ・フリーランスの退職金制度として利用でき、掛金は全額所得控除対象 ・月1,000円〜70,000円の範囲で自由に設定できる |
| iDeCo(個人型確定拠出年金) | ・自分で年金を積み立てる制度であり、掛金が全額所得控除となる ・掛金は原則として60歳まで引き出せない点に注意する |
| 国民年金基金 | ・国民年金に上乗せする形で、老後の受け取り額を増やす制度 ・iDeCoと併用はできませんが、こちらも掛金は全額所得控除となる |



2025年時点で、私はiDeCoのみ行っていますが、小規模企業共済についても検討中です
上記の制度はいずれも掛金が全額所得控除の対象となるため、利用すれば資金形成しつつ、所得税や住民税の負担を軽減できます。
加えて、育児中の方は上記の所得控除を利用し所得を下げることで、諸々の所得制限に引っ掛かりにくくなります。



保育料を少しでも下げたい方は、iDeCoを利用しても良いかもしれません
ただし、上記の制度はあくまでも老後や廃業に向けた資産形成を目的としたものであり、掛金を自由に引き出すことはできません。
そのため、継続的に積立できそうかどうか、老後まで掛金を引き出せなくても資金繰りに問題はないか考えておく必要があります。
【4月】固定資産の購入計画を立てる
比較的、金額の大きな節税対策として固定資産の購入が挙げられます。



パソコンやソフトなど、イラスト制作・販売に使用するものであれば、経費として計上可能です
一方、購入する固定資産によっては金額が大きく、資金繰りに影響を及ぼしかねません。
「高額なパソコンを購入した結果、生活が苦しくなった」なんてならないようにするためにも、今年の売上予測をもとに購入予定の固定資産をリストアップしておくことをおすすめします。
特に、パソコンなど業務に必要不可欠であり、数年おきに買い替えが必要なものは、購入タイミングを見越して予算を立てておくことも大切です。



計画しておくことで、コスパの良い機器を選びやすくなったり、セールの時期を見越して購入できたりします
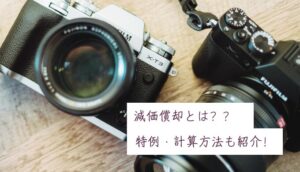
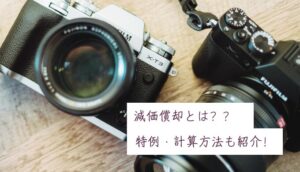
【5月】住民税・国民健康保険の通知を確認する
5月頃になると、自治体から前年の所得に基づいた住民税・国民健康保険料の通知が届きます。



自治体によって通知が届く時期に若干差があるので、事前に確認しておくと安心です
個人事業主やフリーランスとして働いていると、住民税と社会保険料は大きな固定費となるので金額や支払い時期を把握しておきましょう。
住民税は、前年の確定申告で申告した所得額をもとに計算され、原則として6月から翌年5月まで年4回に分けて納付します。



会社員と異なり給料から天引きされるわけではないので、納付漏れにご注意ください
国民健康保険も同様に、前年所得に応じて保険料が決まり、年10回に分けて請求されます。
【5月】サブスク契約の見直しをする
毎月発生する定額のサブスクリプション費用も、契約数が増えると大きな出費となるはずです。
5月になり、新年度の慌ただしさが落ち着いたら、サブスク契約の見直しをしても良いでしょう。
- 本当に使っているか
- 費用対効果があるか
無料期間終了後に自動課金されているものや、複数サービスで機能が重複しているものがあったら解約を検討しましょう。
なお、イラスト制作・販売の業務に直結するサブスク契約であれば経費として計上できます。



クラウド会計などの料金も経費として計上可能です!


【6月】ふるさと納税をする(1回目)
所得税や住民税の節税対策として非常に効果が大きいもののひとつが、ふるさと納税です。



寄付上限額内であれば、自己負担2,000円で控除を受けられます
加えて、ふるさと納税では、その地域の特産品などの返礼品を受け取れるので、節税+返礼品と一石二鳥です。



私も季節のフルーツやお肉などをふるさと納税でもらっています
6月時点で年収や所得見込みがある程度見えてくるため、この時期に1回目の寄付をしておくと、年末の駆け込みで慌てる心配がありません。
なお、ふるさと納税には①ワンストップ特例制度と②確定申告で控除申請する方法がありますが、個人事業主で確定申告をしている場合には、ワンストップ特例制度は適用できないのでご注意ください。
また、イラスト制作・販売の業務で使用するもの(デスクやパソコンなど)をふるさと納税で受け取ったとしても、寄付金を経費として計上することはできません。
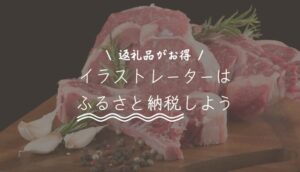
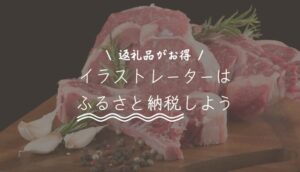
【7月】上半期の売上・経費の集計をする
1月から6月までの売上・経費を7月中に中間チェックしておくと、後半戦の戦略が立てやすくなります。
月ごとの変化を分析し、繁忙期・閑散期を把握することで、今後の案件獲得やスケジュール管理にも役立つでしょう。
また、経費の使い方に偏りがないか、領収書や帳簿の入力漏れがないかを確認する良い機会でもあります。



青色申告の特典を活かすためにも、正確な記帳が不可欠です
クラウド会計を利用すれば、売上や経費の計上も楽に済ませられますし、レポート機能によって月ごとの収益などを分析可能です。
【7月】今年の売上予測の調整をする
上半期の集計結果をもとに、年初に立てた売上目標や収入予測を7月で見直しておくのもおすすめです。
想定以上のペースで売上が上がっていれば、課税所得の増加に伴う税負担にも備える必要があります。



業務に使う固定資産の購入や、費用を掛けてでも業務効率化できないか検討しても良いでしょう
反対に、想定よりも売上が低い場合には、今後の営業方針やスケジュール調整を行う必要があります。



適切なペースで安定した収入を目指すほうが、メンタル的にも余裕を保ちやすくなります
また、売上が1,000万円に近づいている場合は、消費税の課税事業者になる可能性があるため、消費税申告や法人成りについても意識し始めることが重要です。
【7月】固定資産・備品の購入(Primeデー)
固定資産や備品を購入するのであれば、毎年7月に開催されるAmazonのPrimeデーを利用するのもおすすめです。



楽天経済圏を利用している方は、楽天スーパーSALEを利用するのも良いですね
AmazonのPrimeデーでは、PCやiPadなどのガジェットもセールになりますし、デスクやオフィスチェア、プリンターなど何でも購入できます。
Primeデーに購入すれば、キャンペーンを利用してポイント還元も受けられるので、プライベートの品や日用品の購入にも使えます。
【8月】固定資産・備品・経費の入力漏れがないか確認しておく
お盆の時期などで比較的時間の取りやすい8月は、これまでの記帳や経費計上に漏れがないかを確認する絶好の機会です。
特に、フリーランスのイラストレーターは、仕事とプライベートの境界が曖昧になりやすいため、うっかり経費に入れ忘れている支出がないかを丁寧に見直しましょう。
具体的には、以下のような支出が漏れやすい傾向があります。
- 書籍や資料として購入した漫画・雑誌・専門書
- イラスト作成に使用したアプリやクラウドサービスの月額費用
- 打ち合わせや展示会参加時の交通費・飲食代
- 家事按分できるインターネット代、電気代などの水道光熱費(在宅作業が主な場合)
経費として計上できるか不安な場合には、一度税理士に相談してみても良いでしょう。
【9月】ふるさと納税をする(2回目)
6月に1回目のふるさと納税を実施している場合でも、9月になったら年間の寄付上限額を再確認し、余裕があれば2回目の寄付を行いましょう。
ふるさと納税は今年の年収(所得)によって寄付上限額が決まるのですが、会社員と異なり、フリーランスの場合は年収のばらつきが激しく寄付上限額を予測しやすいのがネックです。
- ふるさと納税をしたものの、寄付上限額をオーバーしてしまった
- 思ったより収入が多く、寄付上限額が余ってしまった
上記を防ぐためにも、年に数回分けてふるさと納税を行うことをおすすめします。
【10月】年末までの売上見込みを再計算する
10月になったタイミングで、残り3ヶ月の仕事のスケジュールもある程度決まることも多く、年間の売上着地を予測しやすいでしょう。
この計算によって、年末にかけて必要な節税対策や来年の税金や社会保険料の資金繰りを計画しやすくなります。
【10月】小規模企業共済・iDeCo・国民年金基金の掛金計画の調整をする
10月に年間の売上予測をした際に、小規模企業共済やiDeCo、国民年金基金の掛金を見直すのも良いでしょう。
例えば、思ったよりも所得が増えそうであれば、iDeCoや共済の掛金を上げて所得控除額を増やすことで課税所得を圧縮するのもおすすめです。
反対に、収入がやや低調であれば、無理に掛金を維持するのではなく、負担の少ない金額に一時的に下げて生活費に余裕を持たせることも検討しましょう。
【10月】追加で計上する経費はないか確認する
売上見込みの再計算とあわせて、「今年中に使うべき経費がないか」の棚卸しも行いましょう。
例えば、以下のような経費は、意識しなければ見落とされがちです。
- 業務用の備品やソフトウェアの更新
- サイト制作費やポートフォリオのリニューアル費用
- 展示会参加費や書籍代、講座・セミナー参加費
- 年内に納品予定の外注費や取材経費
パソコンなど業務に必要不可欠な固定資産については、いつ買い替えるのかも考えておくと資金繰りしやすくなります。
【11月】売上が予測を大きく上回れば追加でふるさと納税をする
年末時点で利益が予想より増えるとわかった場合には、年内最後のふるさと納税をしても良いでしょう。



ふるさと納税には、1万円程度で寄付できるものもあります
また、個人で働くイラストレーターの場合、確定申告をするので、ふるさと納税のワンストップ特例制度を適用できません。
確定申告で寄付金控除を申告しなければならない一方で、寄付先の上限がなくなるので様々な自治体に寄付を行えるメリットがあります。
【12月】年内に計上したい経費を支出する
年末に向けて最終的な所得を計算し、年内に購入した方が良いものがあれば購入しておきましょう。
例えば、今年の収入が思ったより多いのであれば、パソコンや画材などを購入してしまうのもおすすめです。



ただし、業務に直接関係する支出しか経費として認められないのでご注意ください
【12月】来年の売上・経費を予測する
最後に、来年に向けて売上や経費の予測を立てておきましょう。
- 継続依頼の整理
- 単発依頼の推移分析
上記のことを行えば、収入の変動が大きいフリーランスでも比較的、収入の予測を立てやすくなるでしょう。
万が一、継続依頼が減ってしまい、来年の収入が減ってしまうことが予測されるのであれば、営業活動に力を入れるなど来年の活動も計画可能です。



フリーランスは収入や仕事が減ってしまうと、金額や内容以上にショックが大きくストレスを抱えてしまうこともあります
気持ちも収入も安定して、細く長く稼ぎ続けるためには、収入や経費の予測をこまめに立てることが非常に大切です。
年間を通して節税対策を行うコツ
フリーランスで働くイラストレーターにとって、節税は年に一度の確定申告だけで考えるものではなく、年間を通して継続的に取り組むものです。



日頃から節税や税金に対する意識を高めておくことが大切です
年間を通して節税対策を行うコツは、主に以下の通りです。
- 固定資産・備品の購入はセール時期を狙う
- ふるさと納税は年に何度か行う
- サブスク契約やiDeCoなどの掛金見直しは定期的に行う
- 自分にとって必要な収入はいくらか把握しておく
それぞれ詳しく解説していきます。
固定資産・備品の購入はセール時期を狙う
仕事に使う機材やツールを購入する際は、セール時期を意識するだけで、出費を抑えながら節税効果も得られます。
例えば、AmazonのPrimeデーや家電量販店の年末セールなどは、イラスト制作に使うパソコンや液タブ、モニターなどの購入チャンスです。
10万円以上のものを購入すると固定資産として減価償却が必要ですが、青色申告者であれば少額減価償却資産の特例を使って30万円以下の品であれば、一括で経費にできます。(年間300万円まで)
ただし、あくまで備品や固定資産は必要なものを必要なタイミングで購入するのが基本です。



節税のために無理やり備品を買うのは本末転倒なのでご注意ください
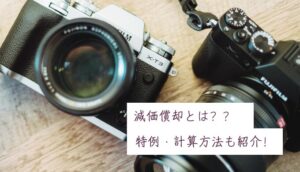
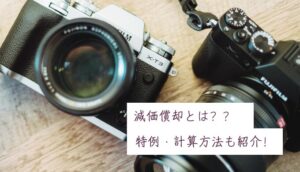
ふるさと納税は年に何度か行う
個人事業主の場合、ふるさと納税を活用するなら、1年に1回まとめて行うよりも、2〜3回に分けて実施するのがおすすめです。
なぜなら、個人事業主は収入の変動が大きく、年の途中で売上や所得が想定より増えたり減ったりするケースも多いからです。



後から寄付上限額に余裕があったと気付いても、年末は返礼品の品切れや自治体の受付停止が起こりがちなのでご注意ください
6月・9月・11月など、年に複数回に分けて実施すれば、返礼品の季節感も楽しめますし、余裕を持って計画的に寄付可能です。
サブスク契約やiDeCoなどの掛金見直しは定期的に行う
個人でイラストレーターとして活動をし続けるのであれば、日々の支出に何気なく含まれている見えにくい固定費も、年間の節税効果に大きな影響を与えるのでご注意ください。
例えば、使ってもいないサブスク契約は解約したり、収入が増えてきたらiDeCoの掛金を増やしたりすることも検討しましょう。
自分にとって必要な収入はいくらか把握しておく
節税を意識する余り「とにかく利益を減らせば良い」と考えてしまうのは危険です。
過剰に経費を計上すると税務署から指摘を受ける恐れもありますし、経費を使うことにより手取りが減ってしまうからです。



個人で働くイラストレーターにとって大切なことは、節税にとらわれすぎず生活の安定をバランスよく両立することです
「できるだけ節税対策をする」と考えるのではなく、まずは、家計の支出や目標貯蓄額から逆算して自分にとって必要な手取り金額(可処分所得)を明確にしておきましょう。
フリーランスは収入上限がないため、働きすぎてしまい、オーバーワークとなってしまう方もいます。
このような事態を防ぐためにも、「どのくらい利益を出せば良いか」「節税のためにどこまで経費を使ってよいか」の判断をしやすくしておきましょう。
個人事業主・フリーランスの税金の支払いスケジュール
個人事業主やフリーランスとして活動している場合、自分で税金や社会保険料を納税しなければなりません。
たとえ売上が多くても、生活費や経費として使いすぎてしまうと、手元に残るお金が減ってしまい、納税資金が足りなくなる恐れもあります。
本章では、個人事業主やフリーランスの税金・社会保険料の支払いスケジュールを解説します。
所得税
所得税は、毎年2月16日〜3月15日の確定申告に基づいて計算され、3月15日までに納付することとされています。



納付方法は、窓口での支払いや口座振替、クレジットカードなどから選べます
なお、前年分の所得税額などを基に計算された予定納税額が15万円を超える場合には、7月と11月に予定納税が必要とされるので資金を用意しておきましょう。
住民税
住民税は、前年の所得に基づいて各自治体が課税し、6月ごろに「納税通知書」が届き、支払いは通常、年4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分けられています。



納税を忘れてしまうのが不安であれば、口座振替にしておくと安心です
消費税
前々年の課税売上が1,000万円を超える場合やインボイス登録をしている場合には、消費税の課税事業者となり、所得税とは別に申告・納税義務が生じます。



消費税の申告は、3月31日が申告・納付期限です。
消費税には「本則課税」と「簡易課税」があり、どちらを選ぶかによって計算方法が変わります。
消費税の計算方法は複雑なので、クラウド会計を利用するか、税理士に申告業務を依頼することをおすすめします。
固定資産税・自動車税
事業に使用しているかどうかにかかわらず、持ち家や自動車を所有している場合には、固定資産税や自動車税がかかります。
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に対し課税される税金であり、自治体によって異なりますが年4回(4・7・12・翌年2月)に分けて課税されます。
また、業務に使用している自動車がある場合は、毎年5月に自動車税の納付通知が届き5月末までに納付しなければなりません。



自動車税は納付書が届いてから納税期限までのスケジュールがタイトなのでご注意ください
また、自宅の一部を仕事場としている場合や、業務でも自動車を使用する場合には、固定資産税や自動車税の一部を経費の一部として計上可能です。
個人事業税
個人事業税は、所得が290万円を超える場合に課される地方税です。
個人事業税の税率は業種によって決まり、イラストレーターはデザイナーに分類されることが多く、税率は5%です。



個人事業税は確定申告を基に計算され、納税通知書が8月頃に届きます


国民健康保険料
会社員と異なり、フリーランスは自分で国民健康保険(国保)に加入する必要があります。
保険料は前年の所得をもとに自治体が算出し、6月以降に納付書または口座振替通知が届きます。
支払いは年8~10回(月払い)であり、6月〜翌年3月まで毎月納めることが一般的です。


国民年金保険料
国民年金は全国一律の定額で、令和7年度(2025年度)は月額17,510円です。
毎月の支払いのほか、6ヶ月や1年、2年の前納制度も用意されています。



前納制度を利用すれば、割引を受けられるため、余裕がある場合はまとめて支払っても良いでしょう
また、支払った国民健康保険量や国民年金保険料は、全額所得控除の対象となるため、毎年10月頃に届く社会保険料控除証明書は大切に保管しておきましょう。
イラストレーターの節税年間スケジュールについてよくある質問
最後に、個人で働くイラストレーターの節税や税金について、よくある質問を回答と共に紹介していきます。
- 個人事業税の納付時期はいつですか?
-
個人事業税は、所得290万円超の個人事業主に対して課される地方税であり、事業の種類によって課税対象が決まっています。
イラストレーターの場合、「デザイン業」や「請負業」に該当する可能性があり、税率は5%となります。
課税対象となった場合、毎年8月上旬〜中旬ごろに納付書が届き、納付期限は8月・11月末日となるのが一般的です。
- 個人事業主が毎年行うことは何ですか?
-
個人事業主は、確定申告を行う必要があり、毎年以下の準備をしておく必要があります。
- 確定申告(2月16日〜3月15日)
- 帳簿の記録と保存
- 各種控除の証明書の整理と保存
- 予定納税(対象者のみ)
- 住民税や国民健康保険料、国民年金保険料の納付
特に、帳簿の作成や各種書類の保管を普段から行っておくと、確定申告の時期に慌てずにすみます。
- 個人事業主の会計期間はいつからいつまでですか?
-
個人事業主の会計期間(事業年度)は、1月1日から12月31日までの暦年であり、期間内のすべての売上・経費・控除を集計し、翌年の確定申告で報告します。
法人と異なり、個人事業主は自由に事業年度を設定することはできません。
【まとめ】年間通して計画的に節税対策をするのがおすすめです
節税は確定申告と異なり、年に一度だけ対策すれば良いわけではなく、年間を通じて計画的に取り組むことが何より重要です。
特に、個人で働くイラストレーターは収入の変動が大きいので、年に何度か売上・経費を予測し、iDeCoの掛金調整やふるさと納税などの節税対策を行っていくと良いでしょう。
また、個人事業主やフリーランスは会社員と異なり、自分で税金や社会保険料を納めなければなりません。
生活費や経費に使いすぎてしまい納税資金が不足したといったことがないように、支払いスケジュールも把握しておきましょう。
本ブログでは、個人で働くイラストレーターに向けて、確定申告や税金、節税に関する情報を発信しています。



ここまで読んでいただき、ありがとうございました

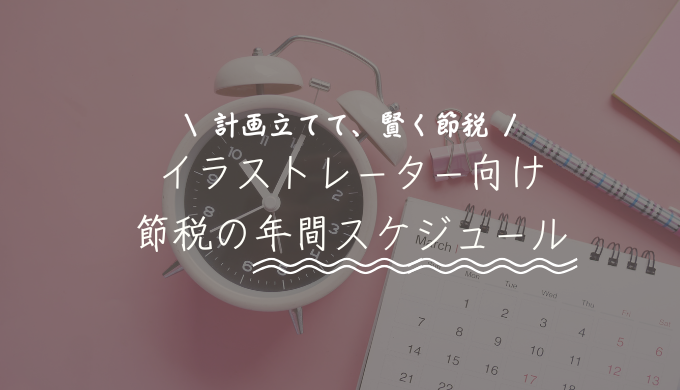
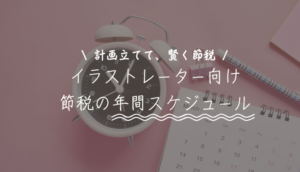
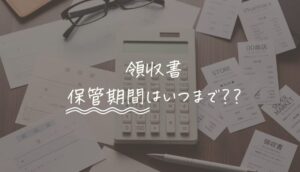
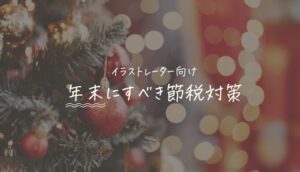
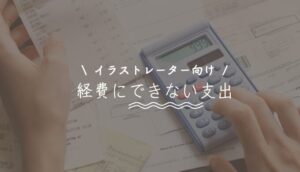
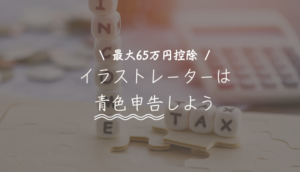
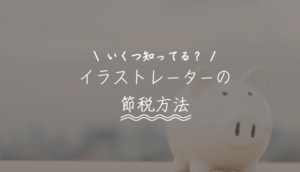

コメント