 お悩み
お悩みイラストレーターとして200万円稼いだら、税金・社会保険料の負担が大きくなってきました……



夫の扶養を出たものの、思ったより手取りが少なく感じます
本記事では、上記のようにお悩みの人に向け、イラスト制作・販売で売上200万円を達成したら税金はいくらかかるのかを解説します。
- 個人で働くイラストレーターが納める税金とは何か
- 年間売上200万円のイラストレーターは確定申告が必要なのか
- 年間売上200万円のイラストレーターは税金がいくらかかるのか
- イラストレーターが節税する方法
イラストレーターに限らず、個人事業主やフリーランスとして働いて収入を得ると、所得税や住民税がかかります。
売上200万円を達成したイラストレーターは、確定申告が必要なケースがほとんどですし、社会保険料も支払う必要が出てくるでしょう。
確定申告シーズンに苦労しないようにするためにも、日ごろから売上や経費を記録しておくことが大切です。
本記事では、売上200万円のイラストレーターにかかる税金はいくらなのかや、節税方法を解説します。
イラストレーターの確定申告については「【保存版】イラストレーターが確定申告する手順【記入例付き】」の記事で詳しく解説しているので、よろしければ併せてお読みください。
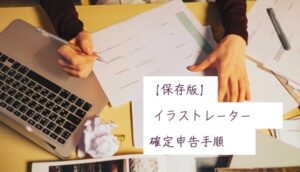
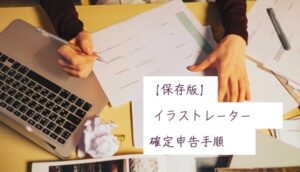
個人で働くイラストレーターが納める税金・計算方法
イラストレーターの売上が200万円を超えてくると、確定申告をして所得税・住民税の計算をしなければならない方がほとんどです。
一方で、個人事業税や消費税については、納税義務がない人もいるでしょう。
本章では、イラストレーターが納める税金や計算方法を解説します。
所得税
所得税は、1年間の「所得額」に基づいて課税される国税であり、「所得」とは、売上から経費を引いた金額を指します。
例えば、イラストを受注して年間200万円の売上があった場合、必要経費が70万円掛かっていたとすると、所得は「200万円-70万円=130万円」になります。



所得税を計算する際には、まず所得金額から「基礎控除」(通常48万円)などの各種控除を差し引きます
仮に、所得が130万円で、基礎控除以外に控除がない場合、課税所得は「130万円-48万円=82万円」となります。
この場合、課税所得82万円に対して適用される税率は、最初の195万円までは5%ですので、所得税は「82万円×5%=41,000円」となります。
このように、売上だけでなく経費を差し引いた後の所得に基づいて、納める所得税が決まります。
住民税
住民税は、所得税と似ていますが、市区町村や都道府県に納める地方税で、前年の所得をもとに計算されます。



住民税の納付は、通常翌年の6月ごろから始まります
住民税の金額は、「所得割」と「均等割」の2種類で構成されています。
- 所得割:所得金額に対して、約10%前後
- 均等割:一律で5,000円前後(地域によって金額が異なる場合がある)
消費税
個人で働くイラストレーターも消費税を納める必要がありますが、すぐに納付義務が生じるわけではありません。
原則として、課税売上高(売上)が1,000万円を超えた翌々年から、消費税の申告・納付義務が発生します。
年間収入が200万円程度であれば、現時点では消費税の申告義務が発生するケースは、ほぼないでしょう。
ただし、2023年10月からはインボイス制度が始まりました。



インボイスに登録している場合、売上に関係なく消費税を納税する必要があるため、注意が必要です
個人事業税
個人事業税は、個人で事業を営む人に課せられる地方税で、一定の所得を超えた場合に発生します。
具体的には、「事業所得」が年間290万円を超えた場合、その超過分に対して3%〜5%程度(業種により異なる)の税率が適用されます。



イラストレーターの場合、通常「デザイン業」に分類され、税率は5%です
しかし、収入が200万円程度であれば、経費を差し引いた所得が290万円を超えることはほとんどないため、通常は個人事業税を心配する必要はありません。


【具体例付】年間売上200万円のイラストレーターにかかる税金はいくら?
年間売上が200万円のフリーランス・イラストレーターの場合、実際にかかる税金は、必要経費や控除の金額によって大きく変わります。
本章では、具体例を出して、年間売上200万円のイラストレーターにかかる税金について紹介していきます。
- 年間売上:200万円
- 必要経費:50万円
- 所得控除:63万円(基礎控除48万円+社会保険料控除15万円)
上記のケースでは、事業所得は「200万円-50万円=150万円」と計算できます。
そして、所得控除は63万円なので課税所得は「150万円-63万円=87万円」であり、所得195万円までは所得税率は5%なので「87万円×5%=43,500円」となります。
そして、住民税は所得割10%、均等割5,000円とすると、下記のように計算可能です。
- 所得割:92万円×10%=92,000円
- 均等割り:5,000円
- 合計:97,000円



住民税は所得税より基礎控除が安く、43万円で計算します
事業所得が290万円未満なので個人事業税はかからず、インボイスに登録していない場合は消費税もかかりません。
- 所得税:43,500円
- 住民税:97,000円
- 合計:140,500円
なお、年間売上200万円を超えると、国民健康保険料や国民年金保険料など社会保険料がかかってきます。



年収200万円程度のイラストレーターの場合、年間社会保険料が10~20万円ほどかかることもあるので、備えておきましょう
年間売上200万円のイラストレーターが節税する方法
年間売上が200万円を超えてくると、徐々に所得税や住民税もかかってきますし、何より社会保険の負担も重くなってくるはずです。
そのため、下記の方法で節税対策をしていきましょう。
- 経費を漏れなく計上する
- 所得控除・税額控除を適用する
- iDeCoを活用する
- 小規模企業共済を活用する
- 青色申告に切り替える
それぞれ詳しく解説していきます。
経費を漏れなく計上する
イラストレーターが税金を節税したいのであれば、経費を漏れなく計上することが大切です。
イラスト制作・販売に使った下記の費用などは、経費として計上できる可能性があります。
- イラスト制作に使用した画材代
- パソコン代・周辺機器代
- イラスト制作のソフト代
- クラウド会計の使用量
- インターネット費用
- スマホの使用料金
- イラスト制作・販売の資料・書籍代
- 自宅の家賃・作業場の家賃
- 自宅の電気代・作業場の電気代
- カフェ・コワーキングスペースの作業代
- セミナー受講費用
- 固定資産税や自動車税
- 損害保険料
経費を計上する場合には、領収書などを保管しておきましょう。



青色申告をする場合、帳簿や領収書類は7年間の保管が義務付けられています
所得控除・税額控除を適用する
経費を漏れなく計上するだけでなく、所得控除や税額控除も漏れなく適用しましょう。
所得税の控除には、下記などのものがあります。
| 控除 | 概要 |
|---|---|
| 基礎控除 | 全納税者が48万円の控除を受けられる |
| 社会保険料控除 | 支払保険料(健康保険・国民年金)を全額免除してもらえる |
| 医療費控除 | 払った医療費が年間10万円を超えたら適用できる |
| 小規模企業共済等掛金控除 | iDeCoなどの掛金を全額控除してもらえる |
| 生命保険料控除 | 生命保険や個人年金保険を支払ったときに一定額を所得から控除できる |
フリーランスとしてイラスト制作・販売をしているのであれば、iDeCoで資産形成しつつ所得税を節税したり、ふるさと納税で返礼品を受け取りつつ節税したりするのがおすすめです。



私もiDeCoは68,000円/月掛けていますし、ふるさと納税でお肉や季節の果物などをもらっています
個人的な話になりますが、我が家は親戚が少なく祖父母も都内に住んでいるため、ふるさと納税くらいでしか田舎のおいしいものを受け取ることができず、ふるさと納税は非常に楽しませてもらっています。
iDeCoを活用する
iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入すれば、掛金全額が所得控除の対象となります。
例えば、月1万円(年間12万円)を拠出すれば、その分だけ課税所得が減り、所得税・住民税の節税効果が得られます。



所得が減ることで、社会保険料も下がる可能性があります!
iDeCoで積み立てたお金は将来年金として受け取れるので、個人で活動するイラストレーターの老後資金形成にも役立つはずです。
小規模企業共済を活用する
小規模企業共済も、iDeCo同様に掛金が全額所得控除となる制度です。



個人事業主が退職金の代わりに活用でき、掛金は月1,000円~70,000円まで選択できます
仮に、月10,000円の掛金を1年間払えば、12万円の所得控除となります。
小規模企業共済は事業を辞めた際や老後に共済金を受け取ることができますが、加入年数によっては元本割れする恐れもあるのでご注意ください。
小規模企業共済については「イラストレーター・フリーランスにおすすめの小規模企業共済とは?」の記事で詳しく紹介しているので、よろしければ併せてお読みください。


青色申告に切り替える
これまで白色申告をしていた場合には、青色申告に切り替えることで所得税や住民税を節税できる可能性があります。
青色申告を適用すれば、最大65万円の青色申告特別控除を適用できるからです。
- 青色申告特別控除(最大65万円)
- 赤字の繰越(最大3年間)
- 家族への給与を経費にできる(事業専従者控除)
ただし、青色申告を適用するには「青色申告承認申請書」をお住まいの税務署に提出する必要がありますし、売上・所得にかかわらず毎年確定申告書を提出しなければなりません。
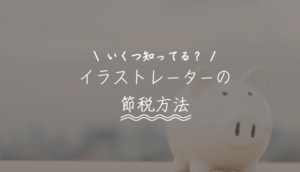
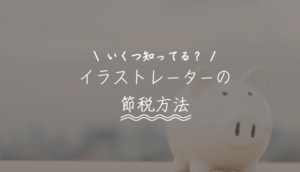
年間売上200万円のイラストレーターによくある質問
最後に、年間売上200万円のイラストレーターが支払う税金について、よくある質問を回答と共に紹介していきます。
- 事業所得200万円にかかる税金はいくらですか?
-
事業所得が200万円ある場合、そこから所得控除(基礎控除や社会保険料控除など)を差し引いた「課税所得」に応じて所得税や住民税が発生します。
仮に、控除が50万円あったとすると、課税所得は150万円となり、税額は下記程度になることが一般的です。
- 所得税:150万円 × 5% = 7.5万円(+復興特別所得税)
- 住民税:約15万円(均等割含む)
実際には、控除の金額やお住まいの地域によっても税額は変わってきます。
- 年収200万円のフリーランスの手取りはいくらくらいになりますか?
-
経費が50万円、控除が50万円だった場合、課税所得は100万円となります。
所得税・住民税を合計して約15万円程度と仮定すると「手取り=200万円-50万円-15万円=約135万円」と計算可能です。
ただし、実際には、上記の金額から国民健康保険料や国民年金保険料なども引かれるため、実際の「可処分所得」はさらに低くなります。
- 年収300万円のフリーランスだと税金はいくらかかりますか?
-
年収300万円で、経費が80万円・控除が60万円(基礎控除・社会保険料等)の場合、課税所得は160万円となり、税額は下記のように計算可能です。
- 所得税:約80,000円(+復興特別所得税)
- 住民税:約16万円
- 合計:約24万円程度
また、事業所得が290万円を超えると個人事業税(デザイン業は5%)も発生する点に注意しましょう。
- 個人依頼でイラスト制作・販売をしても確定申告は必要ですか?
-
個人からイラスト制作の依頼を受け収入を得ている場合でも、所得(売上−経費)が年間48万円を超えると、確定申告をしなければなりません。
- skebで収入を得た際に住民税を申告しないとバレますか?
-
skebなどでの収入も「雑所得」または「事業所得」として扱われます。
申告をしないでいても、銀行に振り込まれたskebの収入などからバレる恐れがあるのでご注意ください。
- 学生がイラスト制作・販売で収入を得たら税金がかかりますか?
-
学生であっても、イラストレーターとしての所得が一定額を超えれば課税されます。
- アルバイトなどをしている場合:所得が20万円を超えたら
- アルバイトなどをしていない場合:所得が48万円を超えたら
所得税・住民税がかかることに加え、イラストレーターとしての収入が増えたら、親の扶養から外れるリスクがあることも理解しておきましょう。
- イラストレーターはいくら稼いだら確定申告をする必要がありますか?
-
イラストレーターは、所得が下記の金額を超えると確定申告をしなければなりません。
- 本業イラストレーター:所得が48万円を超えたら
- 副業イラストレーター:所得が20万円を超えたら
- 青色申告を希望する場合:所得に関係なく確定申告が必要
【まとめ】年収200万円から社会保険料の負担も増えてきます
個人で働くイラストレーターは、経費や控除を差し引いた課税所得に対して所得税や住民税がかかります。
年収200万円の場合、個人事業税や消費税はかからないことが多いでしょう。
一方で、年収200万円を超えてくると、徐々に国民健康保険料や国民年金保険料などといった社会保険料の負担が重くなってきます。
所得税や社会保険料の負担を抑えるためにも、日頃から経費を記録し、所得を少しでも抑えることが大切です。
売上や経費の記録にかかる手間を軽減したいのであれば、クラウド会計の利用も検討しましょう。
イラストレーターにおすすめのクラウド会計は、下記の3つです。
| クラウド会計 | 特徴 |
|---|---|
| やよいの青色申告オンライン | 最大1年間の無料体験が可能 クラウド会計の利用料金を抑えたい方におすすめ |
| マネーフォワードクラウド確定申告 | クラウドワークスなどイラストレーターが利用するサービスとの連携機能が豊富 |
| freee | 簿記・会計の知識がなくても操作しやすいシンプルな機能が魅力 |
どのクラウド会計も無料体験が可能ですので、まずは無料で試してみて自分が使いやすいものを利用すると良いでしょう。




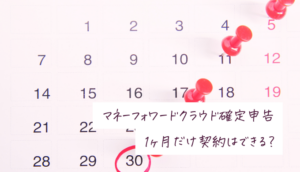
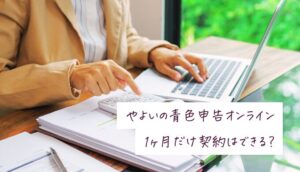

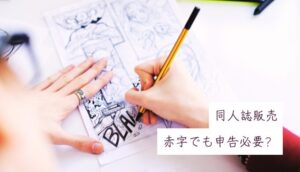
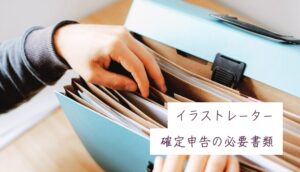
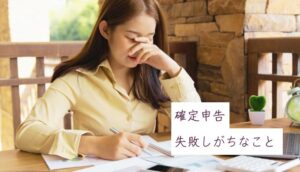

コメント